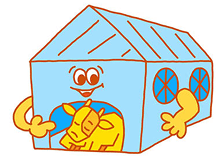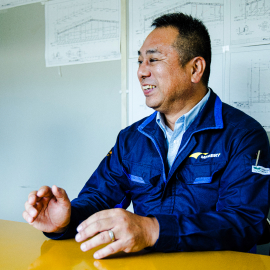私たちはIoTの技術を活用し、畜産や酪農の業務効率化、生産性の向上に取り組んでいます。酪農·畜産に携わる方々は牧草や飼料も生産していることが多く、畑を見に行ったり収穫作業に追われ、どうしても牧場にいる時間が限られます。さらに現在は牧場の大規模化が進む一方で人手不足が加速し、スタッフ1人が管理しなければならない牛の数も増加傾向に。1人で見る牛の数が増えるほど牛の観察は難しくなり、本来は一番大事にすべき発情を見逃してしまうことが多くなります。
畜産·酪農家さんは非常に忙しく、畜舎で牛を見ていて「この牛の個体情報はどうだったっけ?」という時には、数m〜数十mも走るなどして事務所に書類を確認しに行きます。その状況で、1人で管理する牛が50頭から100頭に増えようものならすぐにキャパオーバーになりますよね。積極的にDXを推進しようという農家さんも一部いらっしゃいますが、多くの農家さんは牛の状況を事務所のホワイトボードに書いていたり、人工授精の履歴をノートにつけるなど、アナログ管理を長年続けているのです。
また、肉の品質向上を求めて改良が重ねられていることも牛の身体や牧場の経営に影響をもたらしています。産肉成績を求めた結果、発情行動のわかりにくい牛が増え、繁殖の回転率は落ち、ひいては経営にも悪影響を及ぼしています。
これらの課題を解決していくために、当社ではIoTソリューションという切り口で取り組みを続けています。酪農·畜産生産者向けクラウド牛群管理システムは、これまで紙やホワイトボードで管理していた牛のデータをすべてクラウド上に保存してスマホで確認できるものです。前回の発情や種付けの時期などの情報を牛舎にいながら確認できるほか、いつどの牛にどの種を人工授精したのかという記録についてもスマホから入力できます。これにより、従来の牛舎と事務所の往復が不要になります。入力したデータはリアルタイムで反映されるため、スタッフとの共有も容易になり、スタッフの多い大規模農家さんの運営に寄与します。種付け日を基準とした妊娠鑑定のタイミングや分娩予定日などが自動で通知される機能、夜中の発情を感知する機能も有し、一人で多くのタスクを抱える小規模農家さん、家族経営の農家さんも負担が軽減されるかと思います。反芻が落ちているといった牛の身体の変化を通知する機能もあり、病気の早期発見につながります。


こうしたクラウドの機能を、目の前の課題解決に留まらず売り上げづくりや経営にも役立てていただきたいと私どもは考えており、今後に向けて重要視するのが「牧場経営の見える可」です。たとえば一般企業であれば、まず年間目標を決め、それに基づいたKPIを設定して達成に向けて戦略を立てるといったことを当たり前にやると思うんですが、1次産業ではそれができていないところが多い。つまり、「農家」は多いのですが「農業経営者」と言える方はまだまだ少ないのが実情です。そこにクラウドを投入することで、例えば現在の分娩間隔の状況や牧場全体の発情発見率といった牧場運営に関わる数字が可視化され、全体像や目指すべきことが把握しやすくなります。その結果から「発情発見率が落ちているからセンサーを増設しよう」といった改善策を講じることができます。畜産業をとりまく環境がますます厳しくなる中、何を頑張ればいいのか、どこを改善すればどれくらい良くなるのかという打ち手がわかるのは重要なことです。
IoTの活用は、畜産業·酪農業に携わる方々の肉体面、経営面、精神面の負担を軽減します。将来的には、データを蓄積していくことで、個体ごとに「何頭生んで何頭出荷できたのか」といった長期的な成績までわかるようになります。プレイヤーとして収益力の高い牛をつくることができれば、それを元に他の生産者に販売するといった新たなビジネスも展開できます。マイナスをゼロにすることではなくプラスをつくっていくことが、この先業界を維持していくには非常に重要です。
そういった取り組みを、山口産業さんのようなハードの作り手と共に行うことで広がりが生まれると感じます。膜構造畜舎は、建設時のCO2排出が従来の工法よりも圧倒的に少なく、リサイクルできる建材が使われているなど、未来へ向けて牛と人の良い環境をつくる可能性を感じます。単に2社の製品を組み合わせるだけでなく、新たな物を生み出す、他の企業も巻き込むといったことも積極的に考えても良いのではないでしょうか。